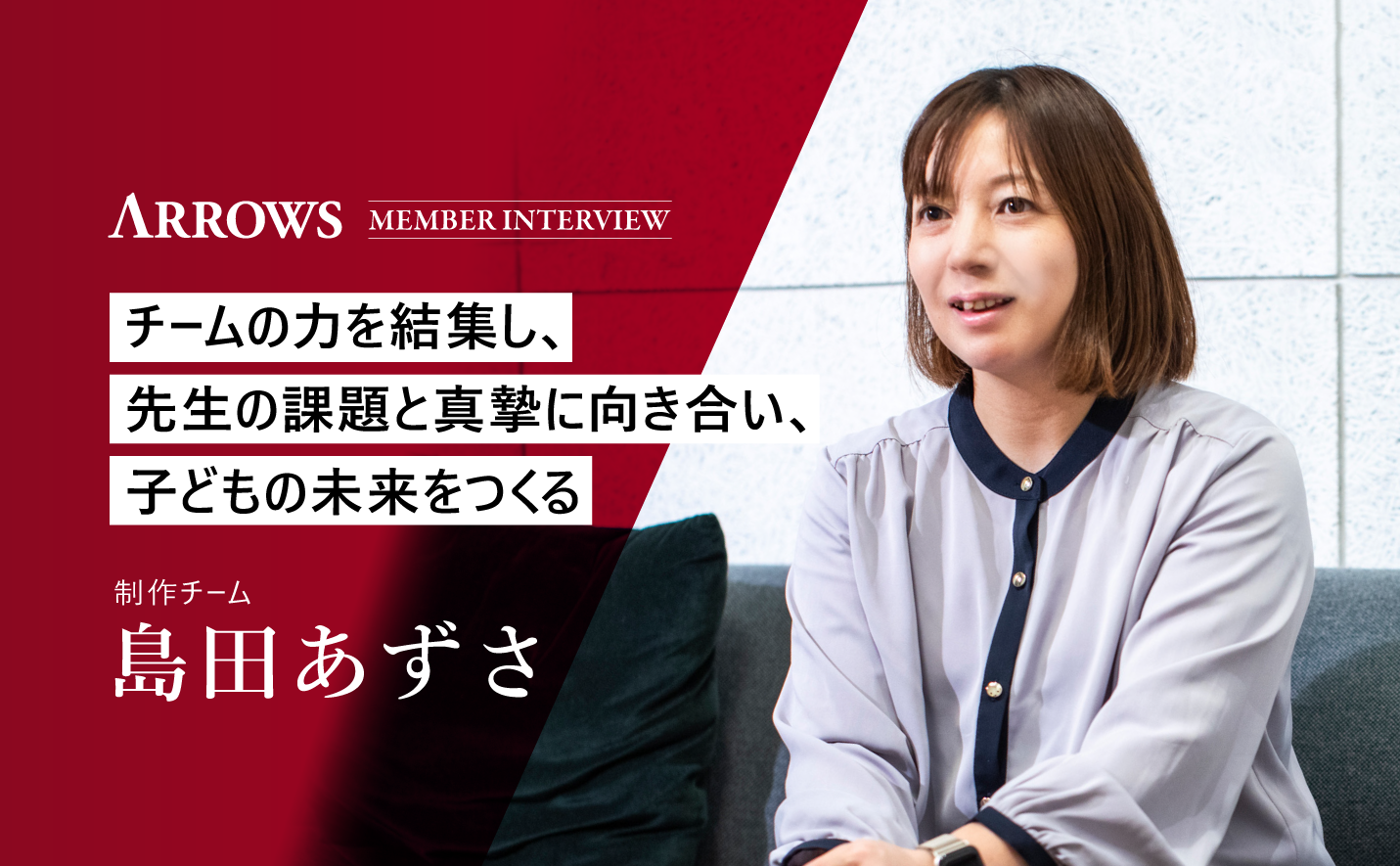
チームの力を結集し、先生の課題と真摯に向き合い、子どもの未来をつくる
「SENSEI よのなか学」の教材制作を担当する島田あずささん。前職でも子ども向け教材に携わった経験を生かし、現在は企業と連携した教材づくりを行っています。先生方のニーズに寄り添い、子どもたちに豊かな学びを届けるため、日々どのような想いで業務に取り組んでいるのでしょうか。今回のインタビューでは、その具体的な仕事内容や背景、制作にかける想いについてお話を伺いました。
profile
株式会社ARROWS 制作チーム 島田あずさ
大学卒業後、株式会社ベネッセコーポレーションへ入社。乳幼児向けのこどもちゃれんじ事業部にて、ダイレクトマーケティングを担当。その後、同事業部にて新規事業の企画開発、ブランド推進、広告やCMなどのマスメディア企画推進、アライアンス事業、事業部内のさまざまなPJリーダーを担当。夫の海外転勤に伴い退社。本帰国後は、前職の会社で小学生向けオンライン英語学習の業務や乳幼児の映像コンテンツに関わる業務に携わる。その他フリーランスとして、複数の企業の業務に携わる。2024年4月より現職にて、学校の先生向けの授業の企画制作を担当。
未来を担う子どもたちに豊かな学びを届けたい
──島田さんは制作チームのメンバーとして「SENSEI よのなか学」の教材制作を担っています。前職でも子ども向けの教材に関わられてきたそうですね。
昔から子どもが好きで、ずっと子どもに関わる仕事がしたいと思っていました。念願が叶い、前職はベネッセで乳幼児向けの通信教育講座「こどもちゃれんじ」に携わりました。初めはダイレクトマーケティングを担当し、のちに新規事業の企画開発やブランド推進、CMなどのマスメディア戦略のほか、さまざまなプロジェクトの推進役として授業に携わりました。家族の海外転勤を機に退職しましたが、帰国後はフリーランスとして、前職の会社を含めいくつかの企業とお仕事をさせていただきました。その頃に、ARROWSからも声をかけてもらう機会があり、業務委託という形で教材制作をお手伝いするようになりました。

──その後1年半の業務委託を経て、ARROWSに入社されました。社員として教材制作に関わりたいと思ったのはなぜでしょうか。
業務委託でオファーを受ける際は企画の骨子や教材の内容などはすでに確定しているため、どちらかといえば制作進行に近い業務を担当していました。スケジュールの管理やデザイナーさんとのやりとりなどが主なタスクです。でも、「SENSEI よのなか学」を深く知るにつれて、子どもにとってより豊かな学びにつながる教材とはどんなものか、先生の授業をより充実させる教材とはどんなものか、どんどん関心が高まってきて、企画段階から関わりたいという想いが芽生えるようになりました。より上流部分から関わることができる社員として、教材制作に力を注ぎたいと思ったのです。ARROWSの制作チームとは業務委託を通して一緒に仕事をしていたので、メンバーの人柄や仕事にかける想いに触れる機会があり、非常に安心できる会社だと感じたことも転職への大きな後押しとなりました。
企業とコラボした教材で授業に新たな視点を
──教材制作で大切にしているのはどのようなことでしょうか。
最も重視しているのは、先生方が今どんなことに困っているのか、教育現場にはどんなニーズがあるのかを把握し、「顧客起点」の考え方に基づいて教材づくりをするということです。そのため、「SENSEI ノート」にご登録いただいている全国の先生方にご協力いただき、ヒアリングや調査などを徹底して行います。「SENSEI よのなか学」の教材をご活用いただいた先生には「授業後アンケート」を実施していますが、そこでいただくご意見にもすべて目を通し、学校現場への理解を深め、先生方のニーズを把握して、次の教材づくりに生かしています。
「SENSEI よのなか学」の教材はすべて企業と連携して制作していますが、企業の知見や最新の事例を教材に取り入れることにより、授業の幅が広がります。子どもたちには、ただ「知って終わり」ではなく、学んだことを「自分ごと化」して捉えてもらえるよう工夫しています。また、日々の業務で忙しい先生方には、ARROWSの教材を活用することで教案づくりの時間を短縮したり、先生方に新たな視座を提供するきっかけになったりすればうれしいですね。そうなれば、子どもたちの学びがもっと豊かになるのではないかと期待しています。

──より良い教材を制作できるよう、どのような努力をされていますか。
学習指導要領や教科書の読み込みです。どちらもARROWSに入社して最初に行ったことなのですが、どの授業でも学習指導要領に基づいて構成するため、欠かせない大切なプロセスです。また、対象学年の子どもたちの発達段階や状況を知ることも重要です。同じ1年間でも4月と3月では成長度合いも異なりますし、中学生・高校生ならどんな時期にあたるのかなどを意識して制作するようにしています。さらに、現場を知るために、先生方にヒアリングを行ったり、実際に学校へ足を運んで授業見学させていただいたりする機会も大切にしています。
教材づくりにおいて「先生ファースト」が第一義であることはゆるがないのですが、一方で、企業の想いをどれだけ伝えられるかという点にも気を配る必要があると考えています。企業が伝えたいことと、学校が求めていることをうまくマッチングできる企画を実現するのは容易ではありませんが、双方の想いを汲み取りながらチームでより良い教材を追求していくことも、この仕事の醍醐味ではないかと感じています。
──島田さんは「SENSEI よのなか学」の事業について、どのような点に共感を持たれますか。
学校の授業というのは、通常であれば一般企業にとって手が届かない場所ですが、「SENSEI よのなか学」により、子どもたちに直接学びを届けられるところが特異であり素晴らしいと思います。企業とコラボレーションすることで生きた情報や新たな視点を提供することが可能となり、それが次代を担う子どもたちの糧になるのであれば非常に意義深いことだと感じます。

アイデアを具現化するチームのちから
──実際にARROWSで働くようになって、会社の印象はいかがでしょうか。
大企業にはないスピードを実感しています。新しい議案が出ると、極めてスピーディに方向性が決まり、会社全体が一つのチームとなって目標に向かっている印象です。実際には営業、CS、制作の3チームに分かれていますが、困りごとが発生すれば、チームの垣根を超えて知恵を出し合う風土があります。先生のために何ができるかを日々模索しているメンバーばかりで、一人ひとりの熱意と目的意識が高いこともARROWSの魅力だと思います。
──ARROWSに向いているのはどんな人だと思われますか。
子どものこと、先生のことを真摯に考えられることが第一条件だと思います。もちろんビジネスなので利益を度外視することはできないのですが、それでも、子どもや先生にとっての最適解を追求する姿勢を忘れてはいけないと考えています。
また、新しいことに挑戦したいという方にとって、非常にやりがいを感じることのできる職場ではないでしょうか。会社の風土として、みんなが新しい意見に対して耳を傾け、柔軟に受け止めてくれるので、誰もが声を上げやすい雰囲気があります。こんなことをやってみたい、という自分のアイデアを具現化してくれる力強いチームの存在も大きなポイントです。チームで同じ目標に向かって挑戦することが好きな人も向いていると思います。
──今後チャレンジしてみたいのは、どのようなことでしょうか。
兄弟が教師をしているので、大変さは肌で感じていたつもりだったのですが、この仕事を通じて先生方の状況を知るにつれて、本当に忙しくて大変だなと感じます。近年は生徒の多様化が進み先生が目配りすべき観点がますます増えていますし、保護者の対応もあります。学校教育現場における「働き方改革」がなかなか進展しづらい現状において、私たちができることがもっとあるのではないかと感じています。「SENSEI よのなか学」の教材をお届けすることに加えて、先生方をサポートできる事業を立ち上げることができたら──。まだ、具体的なアイデアまでたどり着いていませんが、現在の貴重なリソースを活用し、チームの力を結集して実現に向けた一歩を踏み出せたらと考えています。

先生方にヒアリングをお願いすると、みなさん快く引き受けてくださいます。お忙しいにもかかわらずボランティアで時間を割いていただいたうえに、「楽しかった」「勉強になった」と言ってくださることも。そんな先生方と出会うたびに、感謝の気持ちがわき上がるのと同時に、子どもたちのために真摯に取り組む先生方と伴走し一緒に子どもを見守る存在でありたいと、想いを新たにしています。